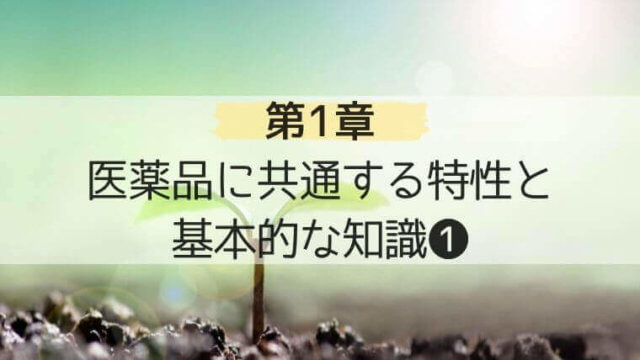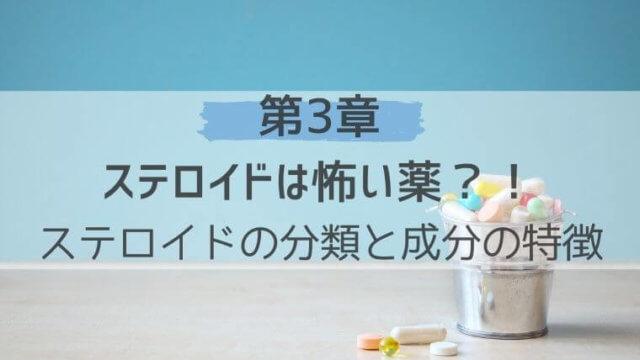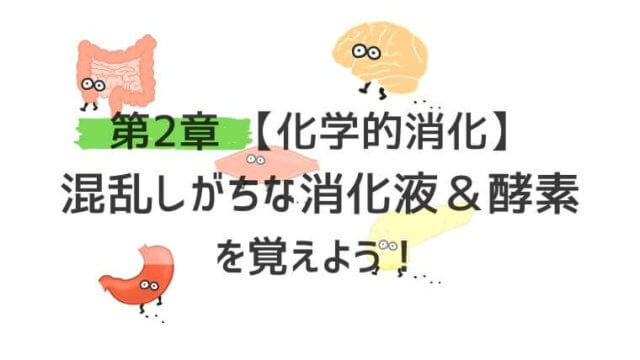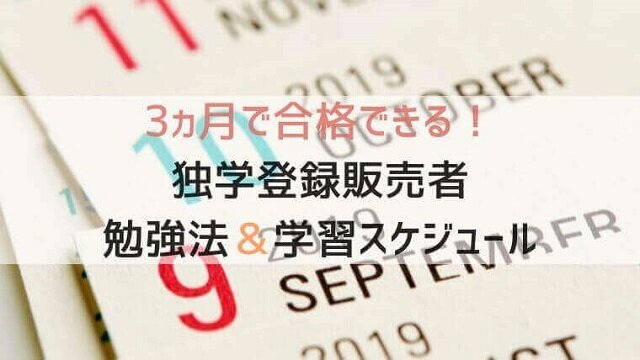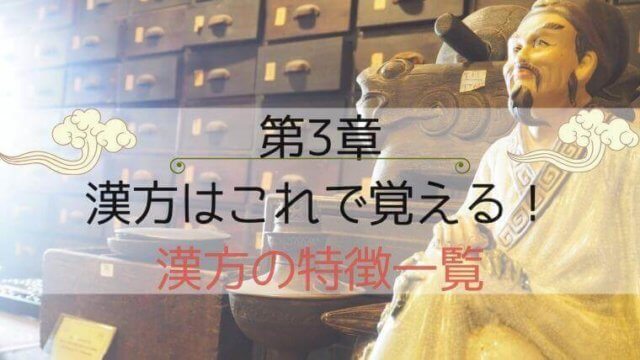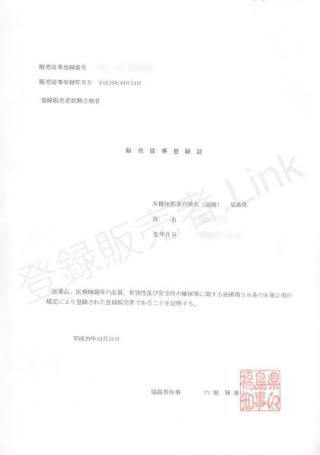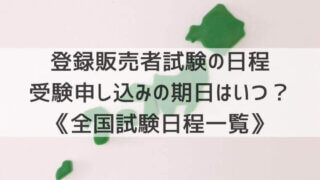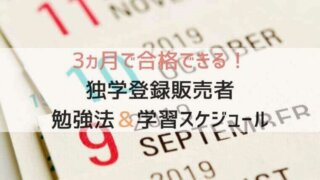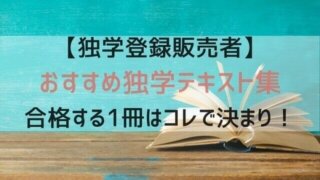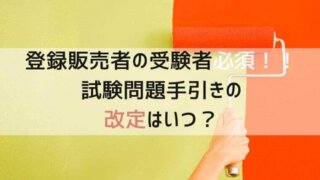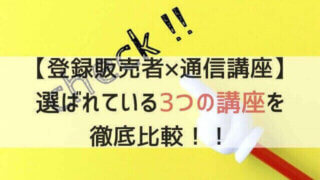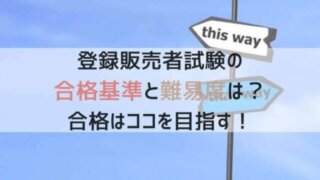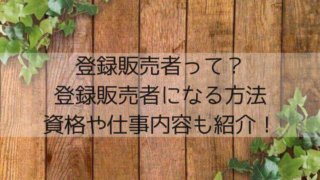前回の第1章:医薬品に共通する特性と基本的な知識 学習法・学習ポイント①
の続きです。
第1章中盤の学習ポイント
難易度:
- 医薬品の副作用の定義
- 医薬品の不適正な使用
- 医薬品の相互作用
- 医薬品の使用の配慮(小児・妊婦・高齢者)
- プラセボ効果
- 医薬品の使用品質の劣化の仕組み
医薬品の効き目や安全性に影響を与える要因
副作用とは
WHO(世界保健機関)での定義では、
疾病の予防・診断・治療のため、または身体の機能を正常化するために、人に通常用いられる量で発現する、医薬品の有害かつ意図しない反応
有益な反応:主作用
好ましくないもの:副作用
副作用の種類・症状・対処
副作用は大きく以下の2つに分けられる
| 薬理作用による副作用 | 薬物が生体の反応に影響を与えること:薬理作用 ※誰にでもおこる |
|---|---|
| アレルギー (過敏反応) | 医薬品の薬理作用とは関係なく起こる 特定の医薬品に対して免疫が何らかの原因で過敏になる ※誰にでも起こるわけではない |
副作用の症状は、簡単に異変を自覚できるものだけでなく、血液や内臓機能への影響など、すぐに明確な自覚症状として現れないこともあります。
副作用が現れたら、初期段階で認識することにより重篤化を避けることが重要です。
一般用医薬品の場合、使用中断することのデメリットより、重篤な副作用を回避する事が優先され、使用を中止する事が基本です。
相互作用・飲み合わせ
医薬品を併用・保健機能食品と併用した場合、医薬品の作用が減弱したり増強したりすること
相互作用には以下の2つがあります。
- 医薬品が吸収・代謝、分布または排泄される過程でおこる
- 医薬品が薬理作用をもたらす部位で起こる
医薬品の適正使用
医薬品は本来の目的以外で、決められた用量を意図的に超えて服用したり、酒類と一緒に飲むなど乱用すると、急性中毒が起こる危険性が高まります。
また、習慣性・依存性がある成分を含んだ医薬品が乱用されることもあり、薬物依存に陥る場合もあります。
医薬品の使用に応じた配慮
小児
乳児:1歳未満
幼児:7歳未満
小児:15歳未満
小児には大人と比べて、
体の大きさに対して腸が長いので、医薬品の吸収率が高く、血液脳関門が未発達で医薬品の成分が脳に達しやすいため、副作用を起こしやすいと言われています。
また、肝臓や腎臓の機能も未発達の為、医薬品の成分の代謝・排泄に時間がかかり、作用が強く出すぎたり、副作用がより強く出ることがあります。
肝臓:医薬品成分の代謝
腎臓:医薬品成分の体外排出
高齢者
高齢者:65歳以上
高齢者は、一般的に生理機能の衰えにより、肝臓・腎臓機能が低下している場合、作用が強く出すぎたり、若年時より副作用が強く出ることがあります。
また、医薬品の副作用で口喝が起きると、嚥下障害(飲み込む力が弱まっている)や誤嚥(食べ物が誤って機関に入る)を起こしやすく、医薬品の服用に際して注意が必要です。
高齢者でも定められてた用量で使用するのが基本
一般医薬品の用法・用量は使用する人の生理機能を含めてある程度の個人差は考えて決められています。
その為、生理機能が衰えていり高齢者であっても、決められた用量の範囲内で使用することが基本です。
妊婦・妊娠している可能性がある方
母体と胎児を繋いでいる胎盤には、血液胎盤関門という胎児の血液と母体の血液が混ざらないようにする仕組みがあります。しかし、医薬品を使用した際に、胎児に影響を及ぼすこともあります。
妊婦などが医薬品を使用する際には、医薬品の成分が胎児に移行するのを防ぐ必要があり、医薬品の使用には充分な配慮が必要です。
しかし、医薬品の成分が胎児に移行するのをどの程度防げるかは、いまだ未解明のことも多く、妊婦に対する安全性に関する評価が困難なため、使用の際は医師などに相談することが重要です。
- ビタミンA:多量摂取により胎児に先天異常を起こす危険性が高まる
- 便秘薬:流産や早産を誘発する恐れがある
プラセボ効果
医薬品を使用した際、
結果的または偶発的に薬理作用によらない作用を生じること
これには結果への期待(暗示効果)・条件付けによる生体反応・時間経過による自然な結果(自然緩解)などが関係しています。
また、プラセボ効果は、不都合な反応や変化(副作用)をもたらすこともあるので、プラセボ効果を目的として医薬品を使用するべきではありません。
医薬品の品質劣化と期限
医薬品にも使用期限(未開封状態で保管された場合に品質が保持される期限)があります。
しかし、適切な保管をしていても、経時変化による品質の劣化は避けることが出来ません。
また、光や高温多湿などによって、品質の劣化起こしやすいのも多くあります。
この為、適切な管理・保管を開していないと、効き目の低下、良くない物質を生じることもあります。
一般用医薬品は、常備薬として購入されることも多いので、使用期限から十分な余裕を持った販売されることが重要です。
第1章:医薬品に共通する特性と基本的な知識まとめ
こちらも常識的に考えれば理解できる内容がほとんどですが、飲み合わせに注意が必要なもの・小児や高齢者、妊婦の特徴・使用での配慮などはしっかり覚えるようにしましょう。
出典:厚生労働省「試験問題作成に関する手引き(令和5年4月)」
をもとに登録販売者.Link作成
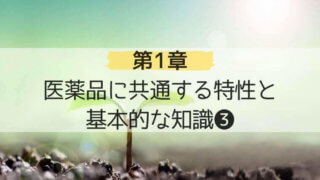
| おすすめ度 | |
|---|---|
| 費用(税込) | 通常コース¥37,700 eラーニング¥44,800 |
| 在籍期間 | 6ヶ月~18ヶ月 |
| 選ばれている理由 | 受験者の要望を総合的に満たしている通信講座! |
PR
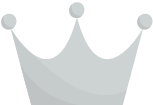 ランキング2位
ランキング2位資格試験初心者にも分かりやすい豊富なテキストや学習カリキュラムで初心者でも安心!理解を深めるならユーキャンで決まり!
| おすすめ度 | |
|---|---|
| 費用(税込) | ¥49,000 |
| 在籍期間 | 6ヶ月~14ヶ月 |
| 選ばれている理由 | 初心者でもじっくり理解を深めてサポート充実! |
PR
| おすすめ度 | |
|---|---|
| 費用(税込) | ¥48,800(WEB申込み限定価格) |
| 在籍期間 | 3ヶ月~12ヶ月 |
| 選ばれている理由 | 不合格の場合全額返金保証あり!(条件あり) |
PR
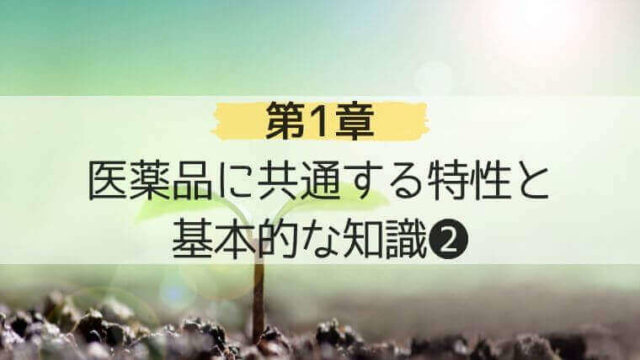

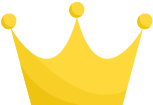 ランキング1位
ランキング1位
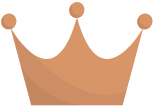 ランキング3位
ランキング3位