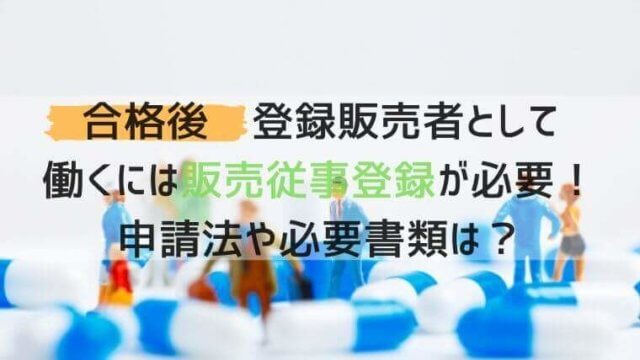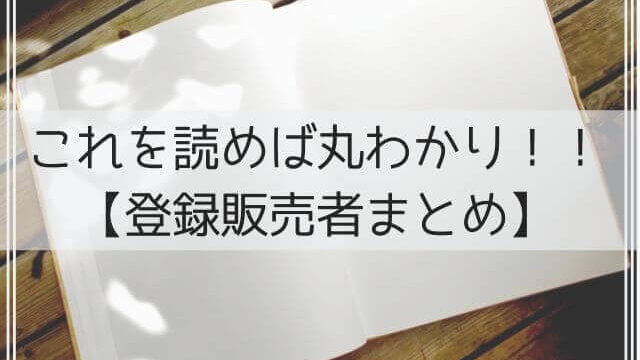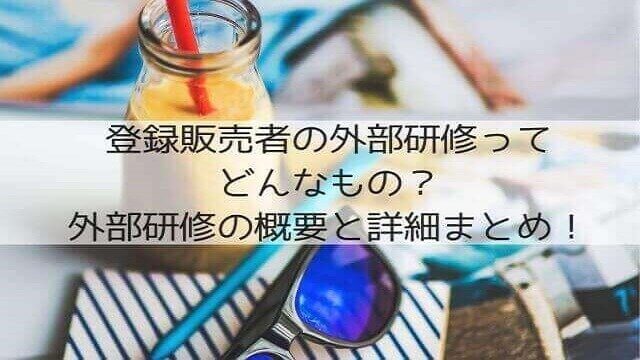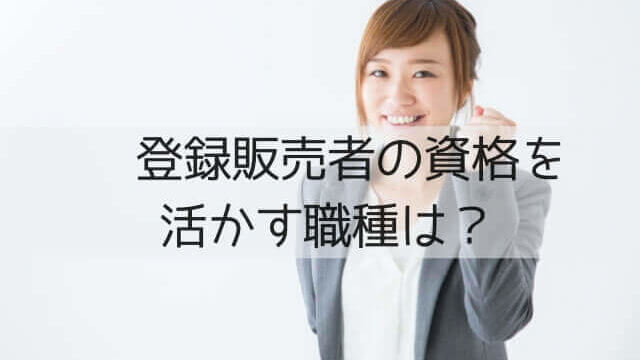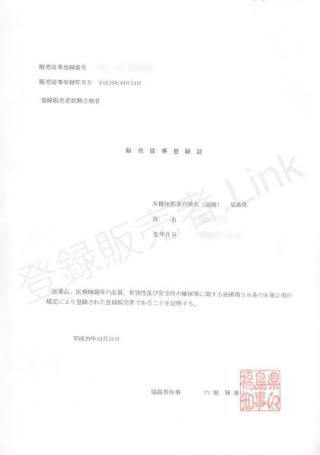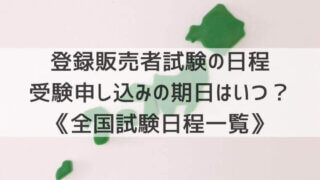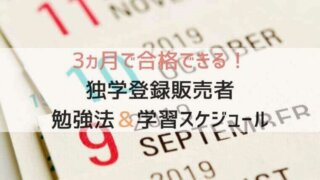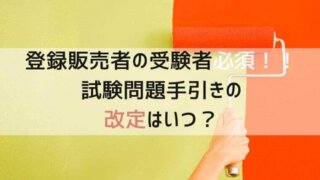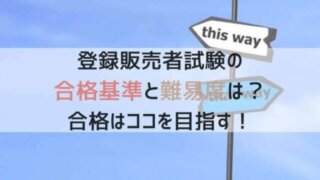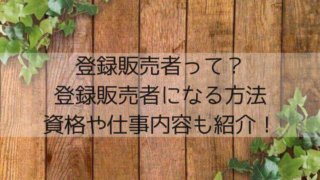令和6年4月 試験作成の手引きの
\改定がありました!/
登録販売者の資格試験問題は、厚生労働省の「試験問題作成に関する手引き」から毎年作成・出題されますが、
この手引き内容が、数年に1度一部改定が行われる場合があるのはご存知ですか?
これを知らないと資格勉強にも大きく影響してきます。
2022年は4年ぶりに手引きの改定が行われましたが…
「せっかく勉強してたのに、内容が変わっちゃうの?!」なんて肩を落とすのは嫌ですよね!
今回は、登録販売者試験の「試験問題作成に関する手引き」の内容を大きく左右する、
改定の時期
改定に対する対策
改定の内容
と!!
2023年(令和5年)の手引き改定に該当する内容の詳細
についてご紹介していきます!
知らなかったとは言ってられない
合格への必須対策です!
登録販売者試験手引きの改定について
 まずは、見逃すことは出来ない手引き改定についての詳細を把握しておきましょう。
まずは、見逃すことは出来ない手引き改定についての詳細を把握しておきましょう。
登録販売者試験問題を作成する際の「試験問題作成に関する手引き」の改定は、定期的に時折年に一度の頻度で行われます。
しかし、改定と言っても一部ですので、長時間をかけて勉強をやり直すほどではありませんが、改定箇所は、その年度からの試験に出題されるなど出題範囲に大きく関わるので、とても重要な内容になります。
では、いつ頃改定が行われ内容が明らかになるのか、詳細を把握しておきたいですよね。
下記で紹介していきますので、しっかり確認しておきましょう!
手引き改定の頻度・目安
 まず、手引き改定の時期について、改定がある場合は以下の時期となります。
まず、手引き改定の時期について、改定がある場合は以下の時期となります。
頻度:数年に1度
目安:3月~4月頃
この手引きの改定は、法改正により起こり、手引改定後は、改定個所とその内容が記された手引きが厚生労働省のHPに掲載されます。
その為、改定の時期にはこちらをしっかり確認しておくことが重要です。
手引きの改定は必ず行われるわけではない
しかし、手引きの改定は必ずしも行われるわけではありません。
先ほども述べた様に、手引きの改定は法改正があった際に起こるため、法改正がない場合は手引きの改定は行われません。
その場合はそのまま学習を進めて問題ないですし、テキストも昨年のものを使用して大丈夫です。
ちなみに直近の手引き改定に関して挙げてみると..
| 平成26年11月 | 改定あり |
| 平成27年4月 | 改定あり |
| 平成28年3月 | 改定あり |
| 平成29年 | 改定なし |
| 平成30年3月 | 改定あり |
| 令和元年 | 改定なし |
| 令和2年 | 改定なし |
| 令和3年 | 改定なし |
| 令和4年 | 改定あり |
| 令和5年 | 改定あり |
| 令和6年 | 改定あり |
このように、必ず毎年改定があるとゆうわけではないんですね。
改定があった場合、
「せっかく勉強してきたのに、改定があった場合はどう対処すればいいの?!」と不安になりますよね。
では、改定が行われた場合はどんな対策が必要かこちらで確認していきましょう!
手引き改定への対策
 受験する年に改定がなされるのか・どんな改定があるのか、こればかりは誰にもわかりません。
受験する年に改定がなされるのか・どんな改定があるのか、こればかりは誰にもわかりません。
しかし、法改正の時期によっては事前に予測として把握できる場合もあります。
それでもいざ受験する年に改定があった場合、何をどうすればいいのか、対策がわかっていれば冷静に対処できます。
実際にどんな対策が必要となるのか下記で見ていきましょう!
改定版テキストの購入
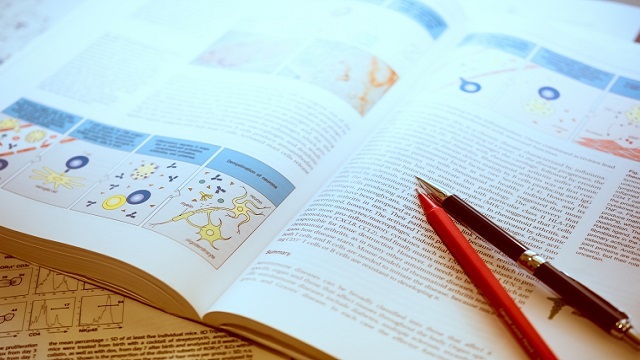 テキストは勉強するにはなくてはならない物ですが、改定があった場合には、改定後に改定版のテキストが発売されます。
テキストは勉強するにはなくてはならない物ですが、改定があった場合には、改定後に改定版のテキストが発売されます。
主に、5~6月や、7~8月頃に改定版として発売されるようになります。
(発売日は出版会社による)
改定版のテキストには「2020年改定版」など、直近の改定の年が記載される
となります。
また、「第○版」という記載のテキストもあるので、発売日などが直近の改定後になっているか・「○年改定に対応」などの記載があるかなどを確認して判断するようにしましょう。
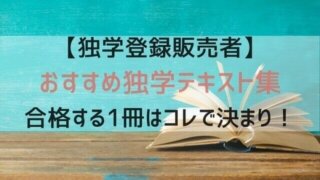
市販テキスト購入後の改定対策
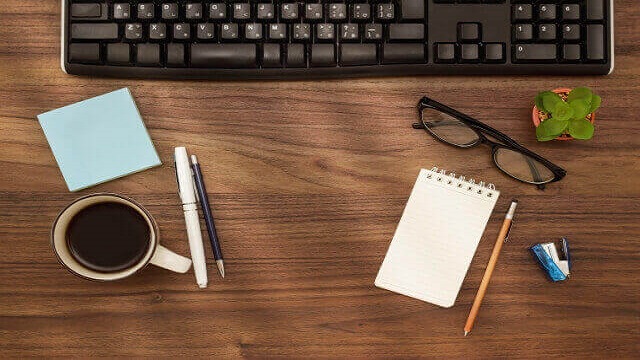 市販テキスト購入後に改定があった場合は、まず厚生労働省のHPで改定履歴入りの手引きを確認しましょう。
市販テキスト購入後に改定があった場合は、まず厚生労働省のHPで改定履歴入りの手引きを確認しましょう。
改定履歴入りの手引きで確認する
改定履歴入りの手引きでは改定箇所が青字で記されています。
それをも元に、市販テキスト内の該当する部分に線を引くなど、改定箇所や改定された内容が分かるようすることが必要です。
もしくは、後に改定対応されたテキストが発売された場合、出版社に問い合わせれば交換などの対応を取ってもらえるかもしれません。(確認はしておりませんので確実なことではありません。)
既に勉強中の方は、改定があった場合はこちらをしっかり確認しましょう!!
購入したテキストの出版社HPで確認する
購入したテキストの出版社HPには「正誤表」等と題したページに、試験作成の手引きの改定内容の概要と、それに伴う、本書における変更箇所や内容が主にPDF形式で掲載されています。
こちらの掲載内容を、該当する自身のテキストに書き訂正をするか、掲載されているPDFデータを印刷し、常に確認できるように手元に置いておくか、この方法で情報を得ることがベストとなります。
詳しくは下記の記事にまとめていますので、市販テキストでの独学者は、必ずチェックしておいてくださいね!
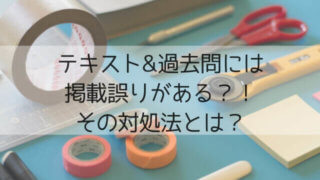
改定版のテキストを購入する
上記以外では、先に述べたように改定版のテキストを購入しなおしてしまったほうが早いです。
自分で改定の内容を抽出し、見分けるのは結構大変。
改定版のテキストでは、改定があった内容を丁寧にまとめてあり、抽出する作業を考えると効率もよく価格も高くはありません。
テキストはいつ買うべき?
そうなると、「改定のあり・なしが確定しから、テキストを購入したほうがいいんじゃないのかな?」と思いますが、答えはNO!です。
なぜかというと、仮に改定があった場合でも、改定版のテキストがすぐ発売されるわけではなく、改定で変更になる内容はごく一部とさほど多くはないからです。
市販のテキストには沢山の種類がありますが、改定があっても、改定版の発売日は5月だったり7月だったり、またはそれ以降だったりとテキストによってまちまちです。
改定の有無を待つのではなく、”改定があっても対応できるようにしておく”ことがとても重要です。
特に、”3章の医薬品の成分”や”2章の人体の構造”など勉強に苦労する章ですが、ここが大まかに改定されることはありません。
改定に当たる多くの部分は、4章や5章の法規が主なので、決めた時期からしっかり学習を開始しておくことがミソとなります。
通信講座の場合
 通信講座の場合は、改定内容や改定に対応した資料などを郵送してくれたりと、きちんと改定に応じた対応があります。
通信講座の場合は、改定内容や改定に対応した資料などを郵送してくれたりと、きちんと改定に応じた対応があります。
通信講座は、サポート体制が整っているためこの点は安心できます。
通信講座は高価格な分、このようなサポートや質問サポートも付いているので、改定があっても安心して勉強に集中できるメリットがあります。
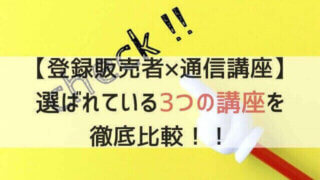
改定を見込んでの勉強
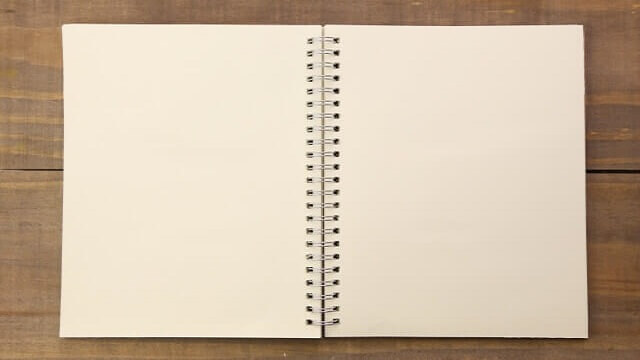 上記でお話ししたように、毎年改定があるかどうかは分かりかねます。
上記でお話ししたように、毎年改定があるかどうかは分かりかねます。
でも、「せっかく勉強したのに変わったらやだな..」と心配の方は、上記で述べた、比較的変更は少ない項目である
- 薬害(1章)
- 人体の仕組み(2章)
- 主な医薬品・作用(3章)
などの学習を先にしておくといいでしょう。
改定内容は、改定される際によって様々です。
しかし、その後の登録販売者試験には、改定内容を踏まえた問題が出題されるようになるので試験範囲に大きく関わるようになります。
改定があった際は、上記で紹介したような対策をしっかり行なっていきましょう。
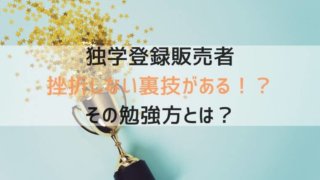
2023年(令和5年)手引き改定の内容
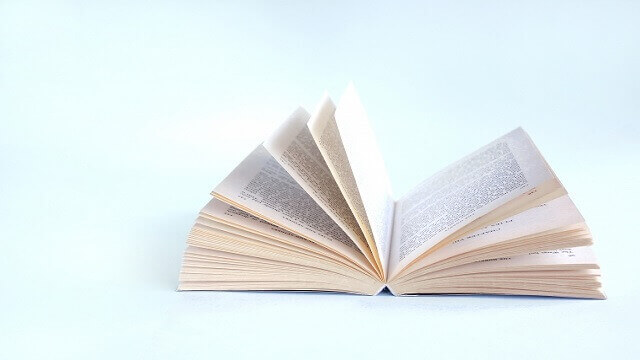 2023年(令和5年)4月1日に”濫用等の恐れのある医薬品”と、”登録販売者の管理要件”との2点について法改正があり、登録販売者試験問題作成の手引きも一部改定となりました。
2023年(令和5年)4月1日に”濫用等の恐れのある医薬品”と、”登録販売者の管理要件”との2点について法改正があり、登録販売者試験問題作成の手引きも一部改定となりました。
詳細については以下でご紹介していますので、しっかり確認しておきましょう!
①濫用等の恐れのある医薬品
まずは濫用等の恐れのある医薬品から確認していきましょう。
従来からの法改正内容は以下の通りとなります。
| 【改正前】 | 【令和5年4月改正】 |
| 1.エフェドリン | 1.エフェドリン |
| 2.コデイン(鎮咳去痰薬に限る) | 2.コデイン |
| 3.ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る) | 3.ジヒドロコデイン |
| 4.ブロモバレリル尿素 | 4.ブロムワレリル尿素 |
| 5.プソイドエフェドリン | 5.プソイドエフェドリン |
| 6.メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち内服液剤に限る) | 6.メチルエフェドリン |
上記6成分を含む医薬品が濫用等の恐れのある医薬品として厚生労働大臣によって指定されていますが、このうち、上記3つの成分の「~に限る」等の制限が外れ、濫用医薬品の範囲が拡大していることがわかります。
上記内容は、登録販売者試験問題作成の手引き第4章の「濫用等の恐れのある医薬品」に係る内容となります。
改正個所としては制限が外れた事のみなので、逆に分かり易くなっています。
しかし、内服薬に限らず上記成分が含まれる外用剤においても濫用医薬品の対象となりますので、簡易的な改正に見えますが、範囲が広がるという意味をきちんと理解しておきましょう!
②登録販売者の管理者要件
登録販売者の管理者要件とは、”研修中の登録販売者”としての期間を終えて、”正規の登録販売者”となる為に必要な要件(必要な実務・業務経験等)のをことを言います。
こちらの従来からの法改正内容は以下の通りとなります。
| 【改正前】 | 【令和5年4月改正】 |
| ●直近5年以内に2年以上かつ通算1,920時間以上の実務・業務経験 | ❶直近5年以内に2年以上かつ通算1,920時間以上の実務・業務経験 ❷直近5年以内に1年以上かつ通算1,920時間以上の実務・業務経験があり、外部研修(年12時間)並びに「法令尊守及び店舗または区域の管理に関する追加的研修(6時間)」を修了 |
これまでは、「直近5年以内に2年以上かつ通算1,920時間以上の実務・業務経験」が正規登録販売者となる為の管理者要件となっていましたが、令和5年4月から❷の新たな要件が追加となり、❶と❷のいずれかの要件を満たせば管理者として認められることとなりました。
第1 登録販売者の管理者要件の一部見直し等
1 改正内容
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施
行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「施行規則」という。)第140条第
1項及び第149条の2第1項の規定により、登録販売者は、過去5年間のう
ち薬局、店舗販売業又は配置販売業において一般従事者(その薬局、店舗
又は区域(以下「店舗等」という。)において実務に従事する薬剤師又は
登録販売者以外の者をいう。以下同じ。)として薬剤師又は登録販売者の
管理及び指導の下に実務に従事した期間並びに登録販売者として業務(店
舗管理者又は区域管理者(以下「店舗管理者等」という。)としての業務
を含む。以下同じ。)に従事した期間(以下「従事期間」という。)が通
算して2年以上の場合(従事期間が通算して2年以上であり、かつ、過去
都 道 府 県 知 事
保 健 所 設 置 市 長
特別区長
に店舗管理者等として業務に従事した経験がある場合を除く。)に、店舗
管理者等になることができることとしている。
今般の見直しにおいては、当該要件に加えて、過去5年間のうち従事期
間が通算して1年以上であり、施行規則第15条の11の3第1項、第147条の
11の3第1項又は第149条の16第1項に定める継続的研修並びに店舗又は区
域の管理及び法令遵守に関する追加的な研修を修了した場合には、店舗管理
者等になることができることとした。また、従事期間が通算して1年以上
であり、かつ、過去に店舗管理者等として業務に従事した経験がある場合
には、店舗管理者等になることができることとした。
引用:厚生労働省「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規 則の一部を改正する省令の施行等について」
より
この管理者要件については、下記の記事で詳しく紹介しています!
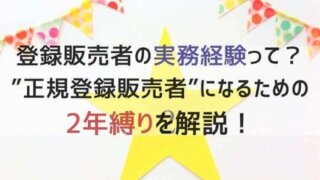
このように、法改正があると試験作成の手引きの該当する箇所も改定され、実際の試験や現場にも影響が出てきます。
しかし、手引きの改定が行われてもほとんどが一部の改定となるので、学習に要する時間はそれほど長くはかかりません。
手引き改定があった場合は、しっかり内容を確認して慌てずに学習すれば問題ありませんので、落ち着いて対処しましょう!
そのために、改定の時期には情報を逃さないようにしておくことが必要です。
登録販売者試験の手引き改定対策のまとめ
今回は、登録販売者試験に関する手引き改定の時期・対策・内容についてお話ししました。
改定に関しては試験のみに関わる内容のように思えますが、実際には医薬品販売の現場にも影響があります。
法改正があった際は、改正内容の確認・手引きの改定箇所の確認をし、しっかり学習することが必要ですが、手引き自体の内容が大きく変わるほどではないので、勉強は始められる時期から始めたほうがいいです。
このことを念頭に入れながら、試験対策としてしっかり対応できるようにしておくことが大切なので、改定の時期にはしかっり情報をキャッチできるようにしておきましょう!

出典:厚生労働省「濫用等のおそれがある医薬品」
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規 則の一部を改正する省令の施行等について」
を参考に登録販売者.Link作成
| おすすめ度 | |
|---|---|
| 費用(税込) | 通常コース¥37,700 eラーニング¥44,800 |
| 在籍期間 | 6ヶ月~18ヶ月 |
| 選ばれている理由 | 受験者の要望を総合的に満たしている通信講座! |
PR
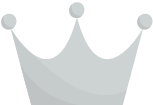 ランキング2位
ランキング2位資格試験初心者にも分かりやすい豊富なテキストや学習カリキュラムで初心者でも安心!理解を深めるならユーキャンで決まり!
| おすすめ度 | |
|---|---|
| 費用(税込) | ¥49,000 |
| 在籍期間 | 6ヶ月~14ヶ月 |
| 選ばれている理由 | 初心者でもじっくり理解を深めてサポート充実! |
PR
| おすすめ度 | |
|---|---|
| 費用(税込) | ¥48,800(WEB申込み限定価格) |
| 在籍期間 | 3ヶ月~12ヶ月 |
| 選ばれている理由 | 不合格の場合全額返金保証あり!(条件あり) |
PR
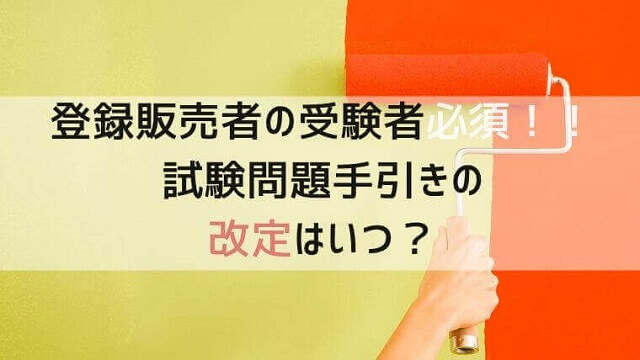

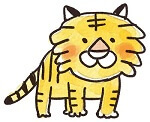
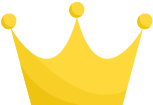 ランキング1位
ランキング1位
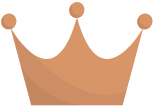 ランキング3位
ランキング3位