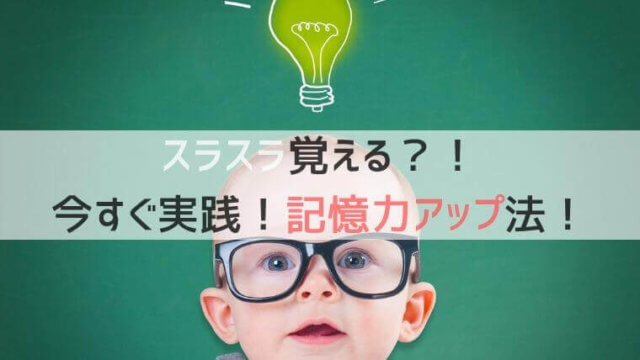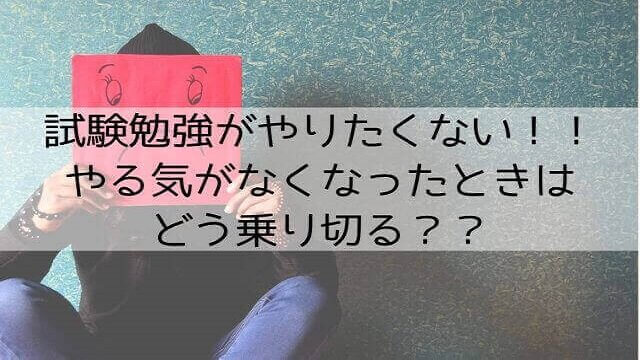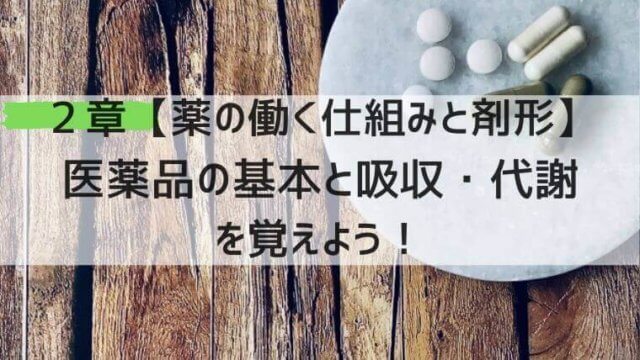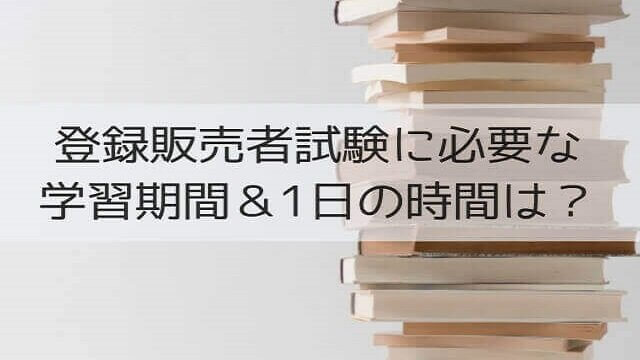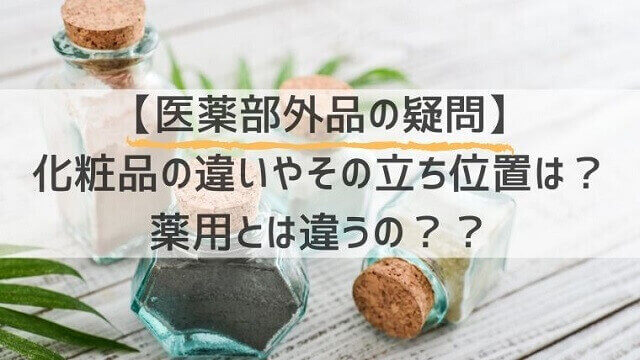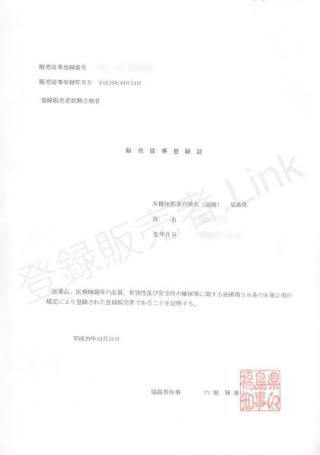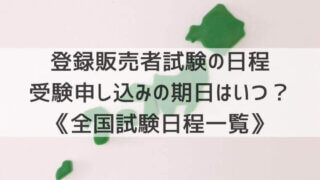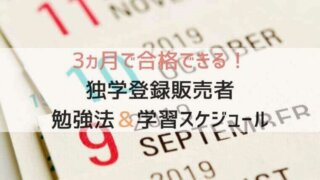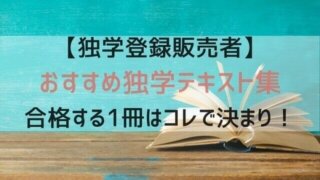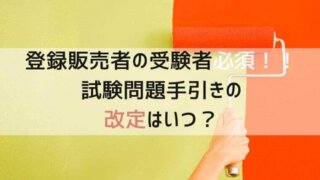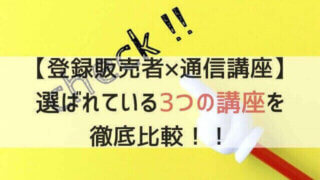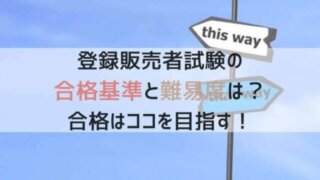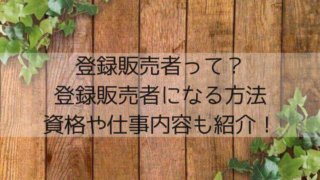いよいよ最終章の第5章の始まりです!
前回は登録販売者試験|第4章:薬事関係法規・制度の覚え方&勉強ポイント!❸です。
医薬品の適正使用情報
添付文書の構成や、記載内容についてしっかり理解しておきましょう。
難しい内容ではないのですが、混在して覚えてしまわないように注意!
その効能効果・用法用量・副作用など、適正な使用の為に必要な情報
のことです。
医薬品はこのような適正使用情報を伴って、初めて正しく使用することが出来ます。
その医薬品を適正に使用するためには、使用者に分かりやすく必要な情報を伝えなければならないため、適正使用情報は、
- 一般の使用者に理解しやすい平易な表現で記載
- 内容は一般的・網羅的
となっています。
適正使用情報には、
- 添付文書(医薬品の外箱の中に入っている文書)
- 製品表示(医薬品の外箱等に記載されている)
とがあります。
それぞれ下記で確認していきましょう!
添付文章
まずは添付文書の構成を理解しましょう。
添付文書の構成は以下のような内容になります。
添付文章の構成
- 改定年月
- 添付文書の必読および保管に関する事項
- 販売名・薬物名およびリスク区分
- 製品の特徴
(必須事項ではない) - 使用上の注意
●してはいけないこと
●相談すること(使用前)
●相談すること(使用後)
●その他注意 - 効能又は効果(一般検査薬:使用目的)
- 用法及び用量(一般検査薬:使用方法)
- 成分及び分量(一般用検査薬:キットの内容や成分・分量や検出感度)
・添加物(必須事項ではない) - 病気の予防・症状の改善につながる事項
(必須事項ではない) - 保管および取り扱い上の注意
- 消費者相談窓口
(必須事項ではない) - 製造販売業者の名称及び所在地
上記の項目が添付文書の構成内容です。
試験では全般的に出題されますが、更に細かく内容が問われる傾向にあるのは、改訂年月・使用上の注意や保管および取り扱い上の注意です。
それらを踏まえながら、ポイントを押さえていきましょう。
添付文章のポイント
添付文書は必要に応じて随時改訂されており、重要な改訂については改訂年月を記載・改訂された箇所を明示することとされています。
改訂に関しては上記内容のみですが、利用者が変更箇所に注意を払うことが出来るようにされているなど、医薬品を適正に使用するためにも重要な情報となります。
医薬品の保管については、誤った保管方法などにより医薬品の化学変化などが生じる場合があるので、適切に保管することが重要となります。
その為、それぞれその医薬品に適した保管方法が記載されています。
シロップ剤や錠剤等・危険物に該当する医薬品はよく問われている箇所ですが、難しい内容ではないのでしっかり理解し点数を取れるようにしておきましょう。
テキストでは文字ばかりでイメージがしづらく、また似たような言葉が多く私は苦手な章だったのですが、勉強のポイントとしては、実際の添付文書もしっかり見ることで理解しやすくなります。
現在添付文書などは、ネットでも確認することが可能なので、自宅に薬がない場合は要指導医薬品・一般用医薬品などの添付文書を検索し、テキストと実際の記載項目を合わせながら確認していくといいでしょう。
記載項目の「してはいけないこと」「相談すること(使用前・使用後)」「その他の注意」の見出しにある、標識的マークの問いや項目内容からは、
- 妊婦や授乳中の方
- 小児に対しての記載
- 副作用の記載順序
についてがよく問われます。
また、「この内容についてはどの項目に記載されているか」のような問いもあるので、まずは各項目記と記載内容をしっかり分けて覚え、こちらでは記載していませんが記載内容の詳細もしっかり覚えておきましょう。
| 項目 | 項目の分類 | 記載内容 |
使用上の 注意 | しては いけないこと | 次の人は使用しないこと |
| 次の部位には使用しないこと | ||
| 本剤を使用している間は他の医薬品を使用しないこと | ||
| その他してはいけないこと | ||
| 相談すること (使用前) | 医師(または歯科医師)の治療を受けている人 | |
| 妊婦または妊娠していると思われる人 | ||
| 授乳中の人 | ||
| 高齢者 | ||
| 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 | ||
| 次の症状がある人 | ||
| 次の診断を受けた人 | ||
| 相談すること (使用後) | 副作用と考えられる症状を生じた場合 |
相談すること(使用後)では、❶一般的に誰にでも起こりやすい副作用(発生部位別)が先 ➋重篤な副作用(副作用名)が後 に記載されている事に注意しましょう。
重篤な副作用が先に書かれていると思いがちなので、間違えないようにしましょう。
効能又は効果は、一般の生活者が自分で判断できる症状や用途などが記載されていて、「適応症」と記載されている場合もあります。
この効能又は効果は、一般用検査薬では「使用目的」と記載されています。
1回の用量や1日の使用回数などが分かりやすく記載されていて、一般用検査薬では「使用方法」と記載されます。
<用法用量に関連する注意>は、用法用量と区別して記載されています。
成分及び分量では、有効成分の名称や分量が記載されています。
一般用検査薬では「キットの内容や成分・分量」や検出感度も記載されます。
ここには、製造販売業者が購入者の相談に応じるための窓口の名称・電話番号・受付時間などが記載されています。
消費者相談窓口の項目は必須事項ではなく、製薬会社というひっかけが多いので注意しましょう!
※上記では、私が個人的に最低限覚えておいたほうがいいと思うものをまとめました。
製品表示(外箱の表示)
次に、製品表示の構成を確認していきましょう!
製品表示の構成
- 医薬品の区分を示す識別表示
- 医薬品の適切な選択に資する事項
●効能・効果
●用法用量
●添加物として配合されている成分
●「使用上の注意」の記載事項
・副作用や事故等が起きる危険性を回避するための記載事項
・添付文書の必読に関する事項
・専門家への相談推奨に関する事項
・医薬品の保管に関する事項 - 使用期限の表示(配置販売:配置期限)
(適切な保存条件の下で製造3年を超えて性状・品質が安定であることが確認されたものは表示義務なし) - 薬機法以外の法令に基づく事項
この中では添付文書と同じように、使用上の注意・使用期限についてが多く出題される傾向にあります。
| 項目 | 項目の分類 | 記載内容 |
| 「使用上の注意」 の記載事項 | 副作用や事故等が起きる危険性を回避するための記載事項 | 次の人は使用しないこと |
| 次の部位には使用しないこと | ||
| 授乳中は本剤を服用しないか本剤を服用する場合は授乳を避けること | ||
| 使用後乗物または機械類の運転操作をしないこと | ||
ポイント 1回服用量中0.1mLを超えるアルコールを含有する内服液剤には、アルコールを含有する旨及びその分量が記載されている | ||
| 添付文書の必読に関する事項 | 使用にあたって添付文書をよく読むこと | |
| 専門家への相談推奨に関する事項 | 使用が適さない場合があるので、使用前には必ず医師、歯科医師、登録販売者に相談してください など | |
| 医薬品の保管に関する事項 | 容器や包装にも保管に関する事項が記載される |
その医薬品の添付文書の記載事項の中から、外箱に上記内容等が記載されています。
添付文書中からの記載なので、添付文書同様しっかり区別して覚えておきましょう!
製品表示のポイント
使用期限に表示されているのは、未開封の状態で保管された場合の期限で、開封されてからの使用期限ではないということをまず理解しましょう。
適切な保存条件で製造後3年を超えて性状や品質が安定であることが確認されている医薬品については、使用期限の表示義務はありません。
また、配置販売の医薬品では「配置期限」と表示されます。
外箱への表示事項は、薬機法に規制されるものだけではなく、
- 消防法(火気厳禁)
- 高圧ガス保安法(高温に注意)
- リサイクル法(包装容器の識別表示)
等の表示もあります。
安全性に関する情報
医薬品などを安全・適正に使用されるために、以下のような
- 緊急安全性情報
- 安全性速報
- 医薬品・医療機器等安全性情報
の安全性情報が出されます。
こちらも違いが分かるように、違いや要点を表にして覚えましょう!
| 緊急安全性情報 (イエローレター) (A4サイズ・黄色地) | 安全性速報 (ブルーレター) (A4サイズ・青色地) | 医薬品・ 医療機器等安全性情報 | |
| 発出 される 条件 | 緊急かつ重大な注意喚起などが必要な場合 | 一般的な使用上の注意の改訂情報よりも 迅速な注意喚起が必要な場合 | 医薬品・医療機器等の重要な 副作用・不具合等に関する 情報を取りまとめた、 医療関係者向けの情報提供 |
| 作成 | 厚生労働省からの命令・指示 製造販売業者の自主決定 | 厚生労働省 | |
| 期限 | 不定期。ただし | ― | |
| 伝達 方法 | ・報道発表 | ・総合機構の医薬品医療機器情報配信サービス | ・各都道府県・関係学会などに冊子で配布 |
| その他 | 一般用医薬品に関する緊急安全性情報が排出されたこともある |
| ― |
総合機構ホームページとは?
添付文書、医薬品・医療機器等安全情報のほか、
- 緊急安全性情報・使用上の注意の改訂情報
- 医薬品による副作用が疑われる症例情報
- 医薬品の承認情報
- 医薬品の製品回収に関する情報
- 一般用医薬品・要指導医薬品の添付文書情報
- 患者向医薬品ガイド・くすりのしおり
- 厚生労働省が医薬品等の安全性について発表した資料
が掲載されており、誰でも利用可能です。
見比べてみると、共通する点が多くさほど難しいものではないですが、医薬品・医療機器等安全性情報や、総合機構の医薬品医療機器情報提供ホームページ(PMDA)については混在しやすい点でもあり、問題でも細かく問われているものもあります。
医薬品医療機器情報提供ホームページ(PMDA)に関しては、どのような内容が掲載されているかが問われることがあるので、実際のホームページも確認して理解を深めておくといいです。
医薬品販売に携わる者として、上記の安全情報にはアンテナを張って注視しておくことも重要で、実務にも直結する項目です!
第5章:医薬品の適正使用・安全対策❶まとめ
今回は、添付文書や安全情報の伝達に関する内容でした。
添付文書はあまり隅から隅まで見たことがない方もほとんどかもしれませんが、初めて詳しく知る内容が多いため、逆に楽しく学べる方も多いと思います。
3章に比べると簡単に感じてしまいますが、項目数が少ない分、細部に渡り問われることも多い章なので、しっかり理解しておく必要があります。
また、テキストの文字だけでは添付文章のイメージが分かりにくいです。
実物で確認できる物に関しては、必ず実物とお手持ちのテキストでの説明内容を見比べながら学習し、それにより理解を深めることが出来るの章なので、是非実践してみてください!
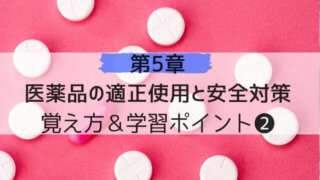
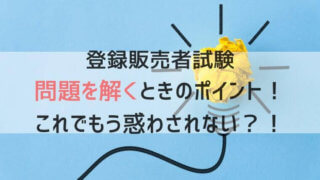
出典:厚生労働省「試験問題作成に関する手引き(令和5年4月)」
を一部参考に登録販売者.Link作成
| おすすめ度 | |
|---|---|
| 費用(税込) | 通常コース¥37,700 eラーニング¥44,800 |
| 在籍期間 | 6ヶ月~18ヶ月 |
| 選ばれている理由 | 受験者の要望を総合的に満たしている通信講座! |
PR
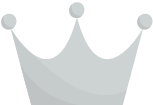 ランキング2位
ランキング2位資格試験初心者にも分かりやすい豊富なテキストや学習カリキュラムで初心者でも安心!理解を深めるならユーキャンで決まり!
| おすすめ度 | |
|---|---|
| 費用(税込) | ¥49,000 |
| 在籍期間 | 6ヶ月~14ヶ月 |
| 選ばれている理由 | 初心者でもじっくり理解を深めてサポート充実! |
PR
| おすすめ度 | |
|---|---|
| 費用(税込) | ¥48,800(WEB申込み限定価格) |
| 在籍期間 | 3ヶ月~12ヶ月 |
| 選ばれている理由 | 不合格の場合全額返金保証あり!(条件あり) |
PR
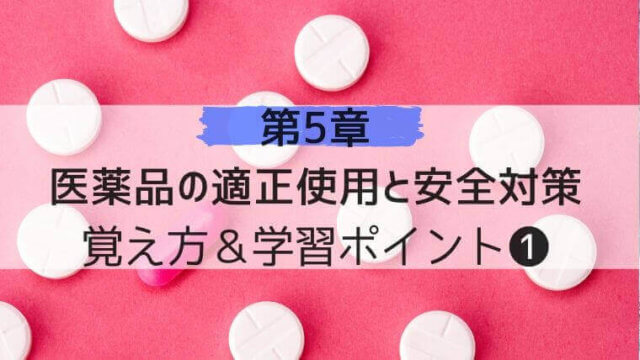

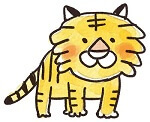
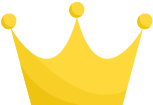 ランキング1位
ランキング1位
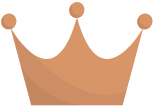 ランキング3位
ランキング3位